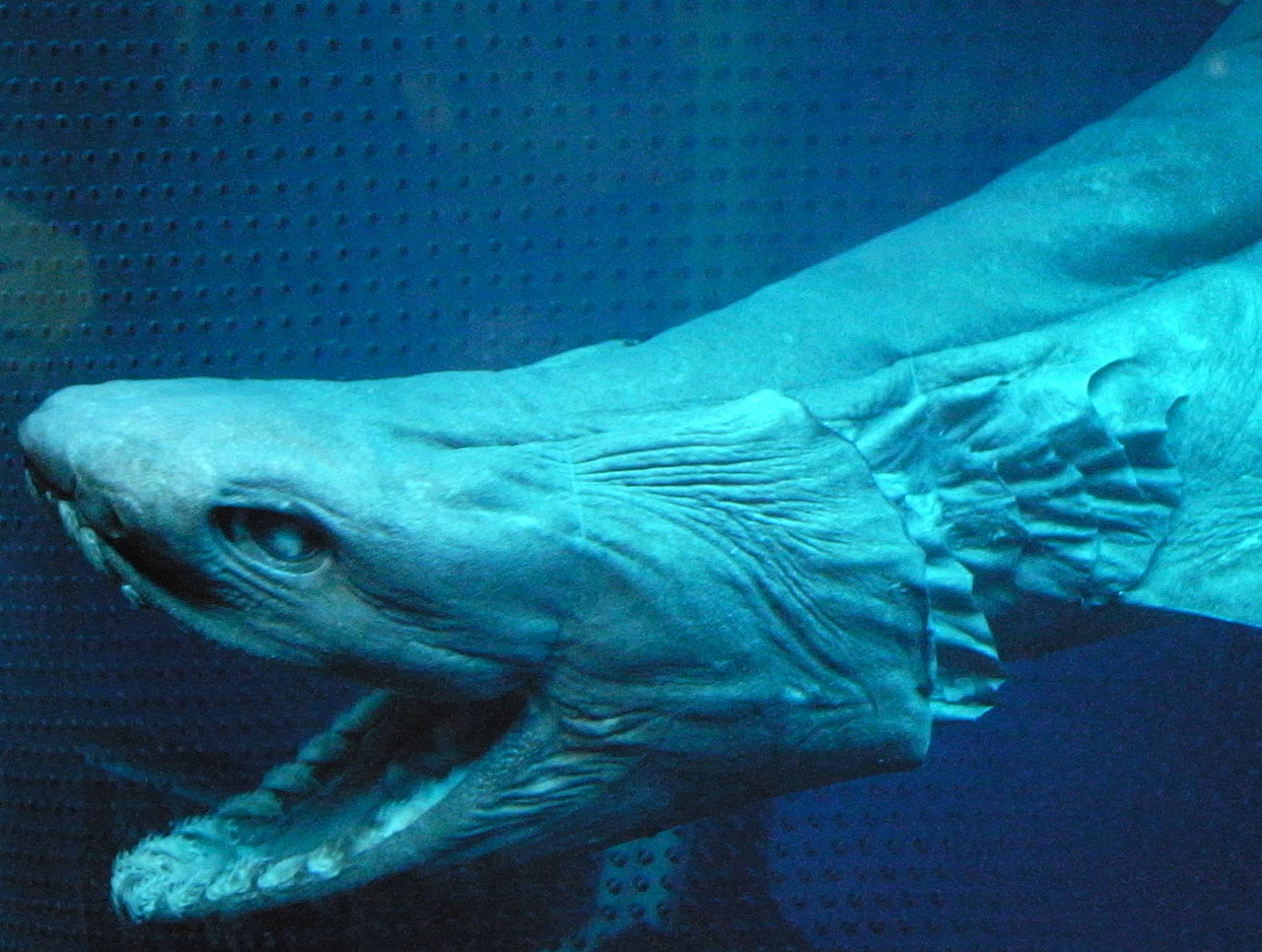日本の豊かな国土は多様な自然を育み、様々な種類の動植物が生息しています。中でも学術上貴重で価値の高いものは「天然記念物」、「特別天然記念物」に指定され、保護、保存の対象となっています。そんな珍しい動植物の中から知っておきたい鳥類5選をご紹介。
日本に生息している珍しい鳥類5選
タンチョウ
出典:おもしろ生物図鑑
ツル目ツル科に分類されるタンチョウは、日本で見られる7種のツル科のうち、唯一国内で繁殖するツルです。日本で最大級の野鳥であり、オスはメスより大きく全長は約140cm、翼を広げると約250cmもの大きさです。
羽毛は全体に白色ですが、長い風切羽は黒く、立っていると白い尾羽を覆うので黒く見えます。頭頂から後頭部にかけて赤いので「丹頂」という名前の由来となりました。
丹は赤をさし、頂はてっぺんをさします。1935年に「天然記念物」、1952年に「特別天然記念物」に指定されました。江戸時代には北海道各地のほか関東地方でも見られたようですが、生息地である湿原の開発と乱獲により、明治時代には激減。
その後、大正時代には絶滅したと考えられていました。現在は北海道東部の湿原で一年中見ることができ、約1500羽まで回復してきていると言われています。
コウノトリ
出典:おもしろ生物図鑑
コウノトリ目コウノトリ科に分類される大型の水鳥であるコウノトリは全長約112cm、翼を広げると約195cmの大きさです。全身が白色ですが、風切羽は黒く、翼をたたむと白い尾羽は覆われて黒く見えます。
黒い太めのくちばしは長く、目の周りは赤色という特徴があり、長い脚は暗赤色をしています。
かつては日本各地で見られたそうですが、1953年に「天然記念物」、1956年に「特別天然記念物」に指定されるも、1970年代には日本で繁殖していたものは絶滅してしまいました。
現在は、兵庫県豊岡市で人工繁殖と野外放鳥が行われており、その中から繁殖するものも出てきているようです。また、まれに大陸から渡りの途中で少数が日本を通過することがあり、その際に迷い込むものも。
世界的に見ても東アジアにしか分布しておらず、その総数は約2000〜3000羽と言われています。
アホウドリ
ミズナギドリ目アホウドリ科に分類されるアホウドリは、1958年に「天然記念物」、1962年に「特別天然記念物」に指定されました。北半球最大の海鳥と言われ、全長は約92cm、翼を広げると約213cmの大きさです。
成鳥は体がほぼ白色で、頭は淡い黄色、翼上面の先の方と尾は黒色。幼鳥は全身黒褐色で、成長するとともに白色の部分が広がっていきます。
海面近くの風速差を利用することでほとんど羽ばたかずに波の上を飛ぶことができ、体の長さに比べると翼が長いこともあり、飛翔する姿はとても優雅で美しいことでも知られます。
羽毛を取るために乱獲され、1947年には姿が見られず絶滅したと考えられていました。現在は伊豆諸島の鳥島、尖閣諸島の一部の島にのみ生息し、約2000羽を超えるまでに回復してきていると言われています。
ライチョウ
出典:おもしろ生物図鑑
キジ目ライチョウ科に分類されるライチョウは全長約37cmの大きさで、約2万年前の氷河時代からの貴重な生き残りと言われています。1923年に「天然記念物」、1955年に「特別天然記念物」に指定されました。
”ニホンライチョウ”とも呼ばれ、ライチョウ科の日本固有亜種でもあります。
年に3回換毛することが知られており、春羽はオスが黒褐色、メスが黄褐色で、夏羽は両方とも山肌になじむ暗褐色、冬羽は尾羽の一部以外は雪山に溶け込む純白になり、いずれも保護色として身を守る役割があります。
飛騨山脈、赤石山脈など日本アルプスの一部にある高山帯の草原やハイマツ林に生息しています。江戸時代には”神の使者”として信仰の対象になり、保護されていた歴史がありましたが、明治時代には乱獲により減少しました。
現在では約3000羽程度が生息しているとみられますが、高山という特殊な環境のため、気温の上昇や天敵の増加などによる絶滅が心配されています。
特に、登山者が増えたことにより、登山道周辺のハイマツ林が荒らされたり、残飯を求めて飛来するハシブトガラスによる捕食、また、気温の上昇で生息範囲が広がったキツネによる捕食やニホンジカ、ニホンザルとの餌の競合なども指摘されています。
メグロ
出典:Photo of the week: March 2013
スズメ目メジロ科に分類されるメグロはメジロの仲間ですがメジロよりひとまわり大きく、目の周りに三角形の黒い模様があるのが特徴です。これがメグロの名前の由来となりました。
全長は約13.5cmで、くちばしは細く、背は緑色、胸から腹にかけては黄色で、尾は緑色です。1910年に国の保護鳥として禁猟になった歴史もあり、1969年には「天然記念物」、1977年には「特別天然記念物」に指定されています。
太平洋戦争や開発による生息地の破壊で減少し、絶滅が心配されています。世界中で小笠原諸島のみに生息するため、日本の固有種である前に小笠原諸島の固有種と言える大変貴重な鳥なのです。
メグロが生息している島のうち、定期船が通っているのは母島だけですが、海岸から丘陵上部まで広く分布しているうえ、人を恐れないことから集落内でも見かけることができます。
外来種の茂っている場所ではなく、母島固有の樹木が形成する森林でのみ繁殖していると言われています。
日本の貴重な鳥類を5選ご紹介しましたが、これらはほんの一部に過ぎず、日本には他にも様々な珍しい鳥類が生息しています。
しかし、絶滅に追い込まれている種も少なくありません。豊かな自然とそこに住む貴重な動植物を守っていくためにもまずは興味や関心を持ってみてはいかがでしょうか?